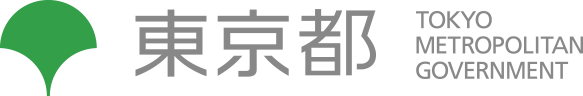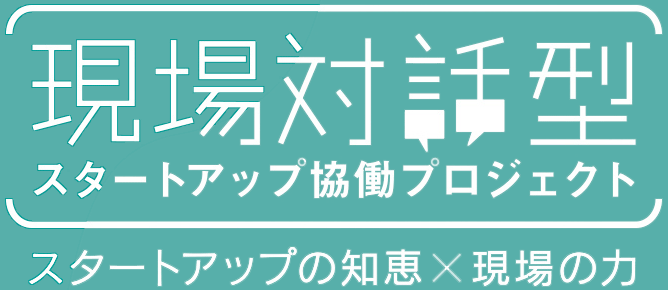令和6年度東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェクト
交通局自動車部 × 株式会社アプリズム 協働ストーリー
〜 協働テーマ 〜
デジタル技術を活用して都営バスの乗降データを効率的に取得し、
路線やダイヤの設定・見直しに活かしたい!
|詳細はこちら|
-
交通局自動車部
交通局自動車部計画課では、都営バスの運転計画の策定や、バス停留所施設の整備等を行っている部署であり、利用状況・運行状況・沿線の開発状況等を調査し、需要の変化に合わせてバス路線やダイヤの見直しを検討・実施しています。
株式会社アプリズム株式会社アプリズム独自開発のOD推定プロダクト「B-RIO」はバス車両内に設置したAIカメラを使用し、バス路線における乗降者数を自動的に集計、可視化することでバス運行のサポート、路線最適化への活用が可能です。
協働プロジェクト紹介
課題背景
交通局自動車部では需要の変化に合わせたバス路線やダイヤの見直しを検討するために都営バスの利用状況を調査していますが、これまでの調査員による乗り込み調査では、調査員の確保や通年でのデータ取得、費用面での負担などが課題となっていました。これら課題を解決するため、機器による利用者の常時把握を目指していますが、現状取得できている情報は一部のICカードタッチデータのみに留まっている状況であり、恒常的に利用者を把握できる機器の導入が求められていました。
ソリューション
バス車両内に設置したAIカメラを活用した、ODデータ※・乗降者数データの取得・集計・可視化
※全乗客がどの停留所から乗ってどの停留所で降りているかの乗降データプロジェクト実施期間
2024年9月~2025年1月
協働の様子プロジェクトの進行
本協働プロジェクトでは、短期間で確実に成果を創出するために、どの路線を測定の対象とするべきか、どのようなプロセスで実証を行っていくべきか、の2点から協議を開始し、1営業所・2台のバスで試験的に測定し課題を洗い出す第1次PoC、5営業所・10台のバスで測定し精度を検出する第2次PoCの2段階でODデータおよび乗降データの収集を進めました。
第1次PoCを開始する前から、交通局とアプリズムで共に都営バスの下見を重ね、前扉から乗車し、中扉から降車する場合のデータを検証するため、機器の設置位置や設置角度の詳細な協議を実施したことで、第1次PoCの段階で問題無くODデータ・乗降データが取得可能なことを確認できました。

第1次PoCで得られたデータと把握した課題を基に、第2次PoCでどの路線を測定対象とするか改めて協議し直し、少しでも測定精度を向上させるための実証方法の見直しを図りました。

そして、約2週間の第2次PoCにて得られたデータを分析し、精度が高く出る路線の特徴の把握、および、精度が低く出る路線の特徴の把握と精度改善方法について議論を行い、今後のさらなるプロダクトの有効活用に向けて検討を進めました。

また、発展的な課題である、乗車券種別の利用者数の把握につながる、乗車券分類の実証実験も実施。机上に置いて乗車券カバーが無い状態で実証を行い、どの程度正確に測定できるかの確認を行いました。また、条件を変えた検証方法の検討、および精度を高めるための乗車券種の望ましい姿など、都営バス利用者の効率的な把握に向けて、来年度以降の都政現場の課題を見据えた長期視点での議論を行いました。

プロジェクトの成果成果
停留所別乗降人数の乗車は約91%、降車は約90%、ODデータは約65%の精度で測定できることが確認できました。さらに、精度の低い路線における原因の洗い出しと対応策について協議の上方針を固めました。また、乗車券種別の分類では、机上での実証においては問題無く読み取り可能なことが確認できました。
今後の展望
今回の協働では、都政現場とスタートアップが「対話」を繰り返すことによって、都政現場の現状課題だけではなく今後クリアするべき課題まで見据えた、将来視点での実証にまで取り組むことが出来ました。協働プロジェクト終了後、交通局からは「機器の取り付けや乗車券種別の分類など、ここまで深くかつ柔軟に連携頂けるとは思っていなかった。短い期間で想定以上の成果を創出頂いた」との声が、アプリズムからは「東京都ならではの条件下における実証実験は、全国展開に向けて新たな課題を発掘できる貴重な機会となった。今回の課題を解決、改善していくことでさらなる利用価値を見出だせた」との声が上がりました。今後も、本プロジェクトで判明した課題を検証し、測定精度の改善に向け、引き続き連携していきたいとのことでした。